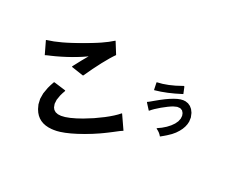部下を育てる上司が絶対に使わない残念な言葉30
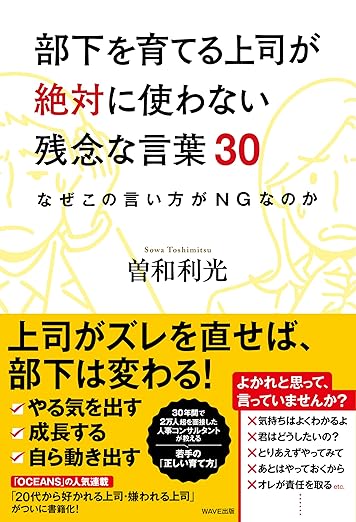
どうしてこの本を選んだか
最近、業務で指導する相手が増えてきた。自分も駆け出しの頃から成長し、今では人に指示を出してタスクを任せ、それを成果物として提出させる機会が増えた。指示する立場になったことで、相手にどう思われるか、またどういう指導が正しいかを客観的に判断する必要があると感じた。
しかし、後輩からのフィードバックを期待するのは難しい(言いづらいだろうし)、この部分については自分自身で掘り下げる必要がある。日常業務の中で、つい嫌味っぽくなってしまいそうな言葉遣いを知り、改善したいと思ったのがこの本を手に取ったきっかけだ。
概要
この本は、現代の若手社員を正しく育成するための指南書である。著者は30年間で2万人以上を面接してきた人事コンサルタントであり、令和時代における若手社員への適切な接し方を提案している。
「理解しよう」と努めるよりも、価値観の違いを素直に受け入れることが重要だと説く。部下に対して不用意に発する言葉が信頼を損なうことを指摘し、以下のような発言をNGワードとして挙げている。
- 気持ちはよくわかるよ
- 君はどうしたいの?
- とりあえずやってみて
- あとはやっておくから
- オレが責任を取る
これらの言葉は、一見すると親切や配慮を示しているように見えるが、実際には部下を不安にさせたり、誤解を与えたりする可能性がある。本書では、若手社員が納得し、自信を持って業務に取り組めるような指導方法を具体的に解説している。
感想
本書では、部下を育てる上司が「絶対に言わない言葉」として30項目が挙げられている。具体的には、このようなセリフを言うと部下に嫌われてしまうといった例が紹介されているが、それはあくまで本の各項ごとのサブタイトルにすぎない。どちらかというと、こうした言葉を使った場合に「なぜ嫌われてしまうのか」という背景部分を丁寧に説明している内容だ。
単なる表面的な「こういう言葉を使うと残念な上司と見られるよ」という話ではなく、「今の世代はこういう考え方で働いている」「こういう行動をすれば部下が育つし、やる気も出る」といった人材教育的な視点で解説されている。そのため、安直に30個の言葉を並べて「それっぽい説明を加えた」だけの内容ではなく、心理的な背景や人材教育の基本について細かく説明されている点が良かった。
逆に言えば、この本で指摘されるような点がしっかりできていれば、例として挙げられている言葉を使っても大きな問題にはならないだろう。また、そもそも嫌な上司はこの本を読まないとも感じる。したがって、本書は「嫌われない上司になる」ための指南というよりも、「人を育てたい」と考える人が読む本だと感じた。
今後への活かし
本を読む中で、自分が考えていたことに合致する内容がいくつか書かれていた。例えば、コンフォートゾーンについての話だ。自分が属している状態が「満足できる状態」であるならば、それは居続けるべき場所ではないということが改めてわかった。
また、部下に対してロールモデルとしてロードマップを示すことが重要だと感じた。今、一緒に仕事をしている目下の人たちには、明確なロードマップを示してあげたいと思う。一旦、それを実行に移してみたい。
Notes
人は「個としての自分が認められ受容された」と感じてから初めて成長する準備を始めます。
世代などの雑で大枠の属性ではなくその人個人の特性を見極めることをどうか心がけてください。新人類という言葉をご存知でしょうか。
ある世代を指す言葉として使われていたものです。
その特徴は「組織よりも個を重んじ、自分の好きなことを尊重する」「社会への関心は少なく、割と従順」「マニュアルを求めてそれに順応しやすい」「ゲームやアニメアイドルなどのサブカルチャーが好き」です。
さて、これらは今の若者にも当てはまる部分かもしれませんか。
種明かしすると「新人類」とはおおむね1955年から1964年に生まれた世代の、すでに全員が還暦を超えています。
このように世代が違っても似た部分は意外に多いものです。
日本は世代間の価値観の格差がどんどんなくなっており、これを「消齢化社会」と呼んでいます。
これからは世代差よりも個体差の方が大きくなる時代とも言えます。どうしても「意見」を入れてしまう癖が抜けない。
上から「お前はどう思う?」と問われる毎日から一転、コンサルタントとなった途端に「意見などいらないファクトとロジックだけで話せ」と言われる日々が始まりました。厚生労働省などの統計によると2023年現在、日本人男女の生涯転職経験回数はおおむね3回程度です。
そこには二つの二極化が見られます。
1つ目は、高額所得者と低額所得者は転職回数が多い(中間層はあまり転職しない)。
年収一千万円を超える高額所得者はより大きな報酬やキャリアアップを狙って転職を重ね、また年収300万円程度前後の低額所得者は非正規から正規職員への転身やより充実した福利厚生などによる生活の安定を求めて転職を目指していると考えられます。
「二極化」のもう一つはしない人はしない、する人は何度でもするです。
実際、終身雇用制度がとうの昔に崩壊したとされている中にあって、大企業に限っていれば半数程度の社員は一度も転職しないまま生涯同じ会社に勤め続けています。今の時代の人材育成の方向としておすすめするのは若手人材たちの自己効力感の向上をサポートすることです。
適切な難易度の仕事をアサインして成功体験を積ませたり、ロールモデルをつけて疑似体験をさせてやったり、いいタイミングで適切な賞賛を行うことで自信をつけさせたり、やる気が出るような職場の雰囲気作りをしたりと自己効力感を高める方法はいくらでもあります。コンフォートゾーンとは「そこまで達したならば、早くそこを抜けるべき状態を指す」。
居続けては成長できない。
買ってねー
おすすめ度:⭐️⭐️⭐️⭐️☆