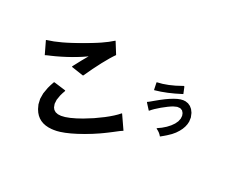モチべーションの心理学-「やる気」と「意欲」のメカニズム
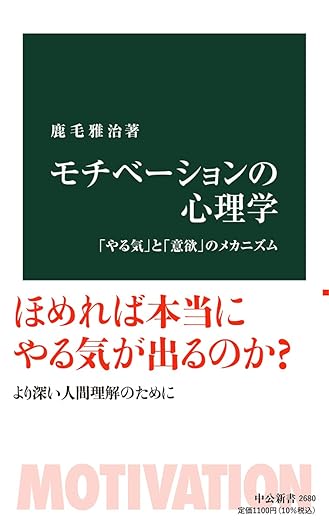
どうしてこの本を選んだか
ピアノの発表会に向けてピアノを練習していたがどうもやる気が出ない。やる気を出さないとまずいのに全然やる気が出ない、どうすればいいのだろう。
そう思ってモチベーションについての本を探したところこの本がヒットしたため購入した。
概要
「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」。人間の場合はなおさらでやる気がない人にいくら無理強いしても無駄である。そもそも、やる気はどう生まれるのか。報酬を与えるのか、口で褒めるのか、それとも罰をちらつかせるのか。自分の経験と素朴な理論で対処しても、うまくいくとは限らない。本書は、目標説、自信説、成長説、環境説など、心理学の知見からモチベーションの理論を総ざらいする。
感想
「やる気」と「意欲」に対して、学術的に知ることができた。具体的にどういうことをすればやる気につながるよとかそういうことを記されたものではないので、具体的なナレッジが欲しい人にはとってはあまりお勧めできるものはないのかもしれない。
ただ、自分としてはそのような研究的な視点から知ることができたのでとても面白かった。
重ねていうが、実際に役に立つ類の本ではない。
今後への活かし
やる気に対しての知識を得ることができたので、他のもっと実用的な本を買おうかなって思った。
Notes
- 外発的動機づけは報酬を得る あるいは罰を避けるための手段として生じるモチベーションの総称で二十世紀半ばまでは モチベーションの支配的な考え方であった。まさにモチベーション2.0に該当する。
- この考え方は体験的にも分かりやすく社会にも広く浸透しているため「飴と鞭」が人に何かをやらせるための方法として半ば自明視されているのも無理はない。
- 金メダルか自己ベストか。モチベーションではそれを「エゴ(自尊)」か「タスク(課題)」かという二分法で考える。つまり、社会的な批判やそれを通した自尊欲求の充足を目的として努力するのか(エゴ)、 それとも 卓越したパフォーマンスそれ自体を目指して努力するのか(タスク)というように、モチベーションを2種類に区分するのである。
- マシュマロテストで高評価の子供はひたすら耐えていたわけではないという点が興味深い。彼らは目の前のお菓子を見ないように手で覆ったり、「待っていればクッキーが二つもらえるよ」と自分に言い聞かせたり、 即興の歌を作って口ずさんといった 涙ぐましい努力をしていたという。
- いくら自分が行動しても望む結果が得られないという体験の積み重ねによって「やっても無駄だ」という非通販性認知が成立してしまったために無力化に陥ってしまったというわけである。このように体験を通して 無気力を身につけてしまう現象を学習性無気力という。
- 問題はこの現象の理論的な説明であろう。 アンダーマイニング効果と効果とエンハンシング効果を同時に解釈する代表的な考え方が認知的評価理論である。その後、この理論を端緒としてディシと彼の同僚のライアンが自己決定理論を主唱し、今日、最も代表的なモチベーション理論の1つへと発展していくことになる。
- 問題はこの現象の理論的な説明であろう。 アンダーマイニング効果と効果とエンハンシング効果を同時に解釈する代表的な考え方が認知的評価理論である。その後、この理論を端緒としてディシと彼の同僚のライアンが自己決定理論を主唱し、今日、最も代表的なモチベーション理論の1つへと発展していくことになる。
- 不潔で不衛生な町はともすると地域住民のモラルの問題つまり人の問題だと思われがちだが、実はシステムの問題だったのだ。 逃げる様を「蜘蛛の子を散らすように」とか「脱兎のごとく」などと表現するが、好きな対象に歩み寄っていくペースよりも危険を感じる対象からの逃げ足の方が早いのである。 罰は不快感情の中でもとりわけ強烈な「恐怖」を引き起こす。 だからその効果は絶大なのだ。
- 笑い声のないところに成功はない。 実業家として 著名な アンドリューカーネギーによるこの言葉は含蓄に富んでいる。笑い声によって場が作られその場が笑い声を誘発するモチベーションとは、このような場のダイナミックダイナミズムの賜物であり、ひいてはそれが成功へと導くのである。
- 一瞬一瞬の状況に正面から向き合い粛々と「今、ここ」に専心して生きる 意欲、いわば「居る意欲」を感じ取ることができるのではないだろうか。
買ってねー
おすすめ度:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️