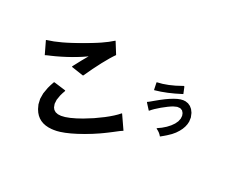ドラッカー名著集1 経営者の条件

どうしてこの本を選んだか
概要
ドラッカー著作の中で、最も広く長く読み継がれてきた自己啓発のバイブル。
自ら成長したい人、周囲とともに目標を達成したい人、すべての人に役立つ内容。
- 成果をあげるための考え方
- 自らの強みを活かす方法
- 時間管理 etc.
世の中の、いわゆる“できる人”が行なっているセルフ・マネジメントの大原則を
「8つの習慣」として紹介。
ビジネスパーソンはもちろん、アスリート、クリエイター、学生、職場からPTA、家庭まで、
幅広く活用されている。
感想
ドラッカーは名著として必ず読むべき本として、多くの人に勧められ、世間的にも広く認知されているだけあって、書かれている内容は非常に勉強になった
組織はどうあるべきか、人員やマネジメントはどうあるべきかといったことが具体的に書かれており、広義でいえば3~4人以上の少人数グループでも、それは組織と呼べるだろう。それに反映させるための具体的なメソッドや心がけも書かれており、小さな組織の単位からスタートさせても十分に優位に働くアドバイスが多く含まれていた。
何より、他の成功著書と同様のことが書かれている点が、その本の信憑性を裏付けると同時に、ドラッカーの著書への信頼感をさらに高めたと感じた。
書かれている内容はすべて有用である一方で、濃密すぎて脳内で処理しきれず、感慨する余裕もなく、ただ目で追ってしまうという場面もあった。
自分の立場や役割が変わったときには、もう一度読み直したいと思える本だった。
今後への活かし
ドラッカーの本に書かれていたいくつかのアドバイスや方針に従って進めていこうと思う。
特に、「よくマネジメントされた組織は退屈である」という点や、「生産性がなくなった作業を見直す」という点は、実際にすぐ取り組める内容なので積極的に取り入れていきたい。
Notes
外の世界への奉仕という組織にとっての唯一の存在理由からして、人は少ないほど、組織は小さいほど、組織の中の活動は少ないほど、組織は完全に近づく。
私は成果を上げる人のタイプなどというものは存在しないことにかなり前に気づいた。私が知っている成果を上げる人は、気質と能力、行動と方法、性格と知識と関心など、あらゆることにおいて共通点は「なすべきことをなす能力」だけだった。
知識労働者が成果を上げるための第一歩は、実際の時間の使い方を記録することである。
よくマネジメントされた組織は日常はむしろ退屈な組織である。そのような組織では真に劇的なことは、昨日の尻ぬぐいのためのから騒ぎではない。それは明日を作るための意思決定である。
成果を上げるには、自らの果たすべき貢献を考えなければならない。手元の仕事から顔を上げ、目標に目を向ける。組織の成果に影響を与える貢献は何かを問う。そして責任を中心に据える。
集中のための第一の原則は、生産的でなくなった過去のものを捨てることである。そのためには自らの仕事と部下の仕事を定期的に見直し、「まだ行っていなかったとして、今これに手をつけるか」を問うことである。
決定が満たすべき必要条件は十分に検討し、選択肢はすべて検討し得るべきものとリスクはすべて天秤にかけた。「すべては分かった。ここにおいて何を行うべきかは明らかである。決定はほぼ完了した」。しかし、決定の多くが行方不明になるのがここである。決定が愉快でなく、評判も良くなく、容易でないことが急に明らかになる。とうとうここで、決定には判断と同じくらい勇気が必要であることが明らかになる。
組織は優秀な人たちがいるから成果を上げるのではない。組織の水準や習慣や気風によって自己開発を動機づけるから、優秀な人たちを持つことになる。
買ってねー
おすすめ度:⭐️⭐️⭐️⭐️☆