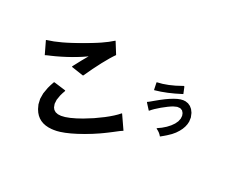私たちはどう学んでいるのか ─創発から見る認知の変化

どうしてこの本を選んだか
Twitter見てたら流れてきた
ちょうど資格勉強しようかなって思っていたので勉強方法を知ろうかなって思ったので買った
概要
人が何かを学ぶときにどういうプロセスで学ぶのかを説明する
上達プロセス
人が物事を繰り返し試行するにつれどのように技術を習熟していくかの仮定
任意のプロセスに対して試行を繰り返すと最初のころは上達がとても早い
試行を繰り返すにつれどんどん上達は遅くなる
上達する過程の中で、特定の手法を繰り返してそれを上達させ、とあるタイミングで成長が鈍化する
その場合は別のより良い手法を取り入れる
最初はその新しい手法を取り入れたことによって一時的に鈍化するが、 その手法も慣れるに従って効果を得られるようになり、その習熟具合は手法を取り入れる前よりもより高い習熟度に落ち着く
子どもの試行と成長過程
子どもにとある課題をかすとき、子どもはどういうアプローチでその課題を解消しようとするかどうか
解法アプローチの差異
課題に対するアプローチはその人が持っている知識によって変わる
知識が多い人ほど初動のアプローチ回数が少ないことが認められる
無意識による解決
人がひらめきを得るのは無意識がその発見の手助けをするという
意識的に考えひらめくのではなく、実際は無意識がそれを発見して意識が明らかにするだけらしい
驚いたことに解放的な身体的動きをす?とそれがより活性化されるとのことだ
素朴教育理論
問題があり、それを解き、答えがあるという単純な演出を素朴教育理論という
素朴教育理論には教師がいて、必ず解放がある
しかし実際の問題はそうではなく、何かに対して思考を巡らせ始めて問題が発程する
当初は問題がないので解放が存在せず、問題を発見して初めて問題になる
当然解放なんてものはない
学校教育はこのような素朴教育理論を使用しているので限定的にしか役にたたない
マイクロ目線な学校的な教育よりも「なんでこうなのだろ」「どうしてこうなるのだろう?」
と言った原因究明的な試行錯誤のほうがより上達度はあがる
感想
人の習熟過程はどういう傾向で上達していくかを興味深い研究と資料を提示しておりとてもおもしろかった
繰り返しを行うことで上達することは当然のことだが、どういう曲線を描いて上達するのか、どのくらいの試行がよいのか、などの具体的な研究データが書かれている本は少ない
本書はそれに関するいくつもの研究を紹介し、興味深い研究データを見ることができた
今後への活かし
繰り返し試行回数の効果の推移のほどがわかった
また、身体の動作が思考にもたらす影響が大きいことがわかった
最近、運動することによって思考力があがる趣旨の書籍が増えたが、本書によりその説が補強された
活発な思考には活発が良い影響があるという点から活動的な身体動作をいっそう心がけようとおもった