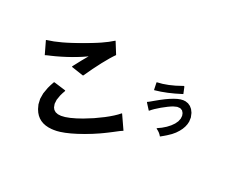痛快! コンピュータ学
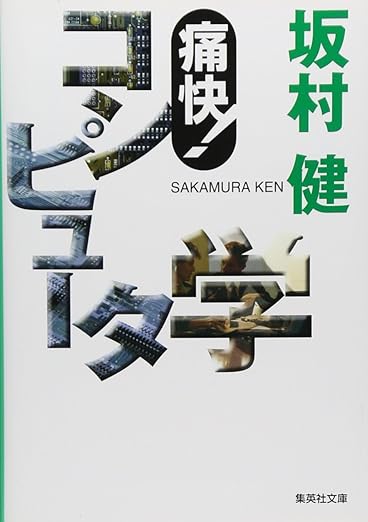
どうしてこの本を選んだか
ツイッターでおすすめの本として紹介するツイートが流れてきたから。 基本的にTwitterとかでおすすめの本が流れてきたら面白そうだと思えばその場で買ってしまうので、この本も例に違わず買った。
概要
21世紀に不可欠となったコンピュータだが、むずかしすぎる。もっと簡単に操作できるように必ずなるが、その根本的なことは理解しなければだめだ。“世界のサカムラ”が解説する決定版入門書!
感想
国産OSの第一人者である著書がコンピュータについて解説した本である。
内容としては、大学の講義相当に相当する内容であるということであるが、結構平素な書かれ方をしており、わかりやすい言葉が使われていたいたいた。自分が理系であるということもわかりやすい内容であった感じるが、もしかしたら普通の人であれば、もう少しとっつきにくいのかもしれない。 ただ、これよりも平素な言葉で書かれたコンピューターについての本というのはあまり多くないだろうと思う。
中でもなにより驚きなのがこの本の第1版が2002年に書かれた内容であるということだ。
現在2024年から20年以上前というと、その頃にはGoogleも登場しておらず、コンピューターというものはそもそもあまり一般的なものではなかった。 驚くべきことに20年前からこのコンピューターの歴史を著者は予測しており、それが今現在その通りになっているということだ。
例えば、オープンソースのプログラムについて。
筆者はオープンソースが今後発達していくだろうと記載しており、実際現在はそのようになっている。
このように、著書は本分野に先見の明を持っており、答え合わせという形で改めて現在の様子と照らし合わせるという読み方もできる。
今後への活かし
コンピューター学に対しての具体的な話というよりは歴史や仕組みについて書かれた本であるため、今後の生かしという部分では難しいかもしれない。
現代はIBMやマイクロソフトの変遷を見るとおり、巨大ベンダーがIT社会を牛耳っている。 おそらく歴史を繰り返すのだろうということを考えると、世界を牛耳ってるITベンダーがどのようなマーケティングを行うかを予想ができそうなものである。
あげるとしたら歴史を踏まえた上で今後の未来予測に役立ちそうな気がする。
Notes
- 猿が打ったタイプの紙と、人間が打ったのタイプの紙、この二つは物理学から見れば物質の構成も光の反射もほとんど同じものです。しかしこれを私たちが見ればその差は歴然としています。物理学で測ることのできない「差」それこそが情報だ。シャノンの情報理論は物理学の盲点をついたものだったともいえるでしょう。
- 情報伝達に本当の革命を起こしたのはやはりコンピュータが発明されてからです。
- ここで申し上げておきますが、コンピューター学をマスターするコツは「とりあえず」分かった気になればそれでいいと考えることです。
- プログラム内蔵方式のコンピューターを別名「フォン・ノイマン型」と言います。「フォン・ノイマン型」は現在でもコンピューターの主流で、もちろんパソコンもゲーム用コンピューターもこのタイプに属します。
- インターネットには全体を管理運営する独裁的な機関はありません。インターネットは誰でも自由に使うことのできるあくまでもオープンなネットです。
- インターネットの翻訳ソフトがまだ上手に訳せないのはどんな文章も訳してしまおうと汎用性を狙っているからです。もしこれが旅行だけということであればかなり役に立つものになると思います。その場合せめてウォークマンぐらいのサイズにならないことには言うまでもないことですが、それは決して不可能ではないでしょう。
- コンピュータのネットワークが発達することによって過密都市に住む必要がどんどん薄れ、好きな場所で暮らしながら好きな時間で仕事ができるようになりつつあるわけです。
- コンピューター技術が人間を幸せにするのか、それとも不幸にするのか、それもまたコンピュータを利用する皆さんにかかっています。
買ってねー
おすすめ度:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️